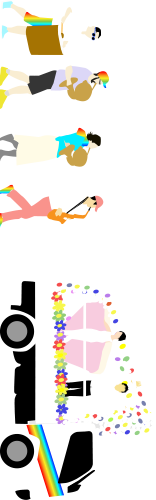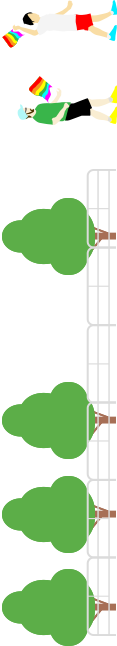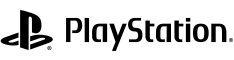5つの残された課題
伴侶盟は2019年で創立10周年を迎え、2020年2月23日、台北市内のホテルで記念チャリティパーティを開催した。

伴侶盟2020年度チャリティパーティで(2020年2月23日)。
 伴侶盟2020年度チャリティパーティで。秘書長・簡至潔さん(左)、常任理事・許秀雯さん(中)と筆者(2月23日)。
伴侶盟2020年度チャリティパーティで。秘書長・簡至潔さん(左)、常任理事・許秀雯さん(中)と筆者(2月23日)。
伴侶盟は当事者を中心とする団体として、最初に婚姻平等化法案を起草するとともに、同性婚を求めるゲイの祁家威氏を代理し、行政訴訟を起こし、大法官に憲法解釈の要請を行うなど、台湾における同性婚法実現の最大の功労者である。その伴侶盟の「2019年度報告書」に「同性婚10年、これからも手を携えて『権利平等』を目指そう」と題する文章が掲載されている(簡至潔、張妤安)。ここで課題を先送りした原因を「アンチ派陣営の強いプレッシャーのもと、あらゆる討論の空間が圧縮されていた」と総括した上で、残された課題を以下のように5つ挙げている。
①台湾人と外国人の同性パートナーとの婚姻への制限
②養子縁組に残る制限
③人工生殖法の適用の可否
④同性配偶者間での姻戚関係の有無
⑤信教の自由規定(同性婚法26条)の危険性
このなかで伴侶盟が現在、もっとも力を入れて取り組むのが、外国人同性パートナーとの婚姻をめぐる問題であり、訴訟が準備されつつある。これについては最後に詳細を紹介することとし、以下では②〜⑤について先に取り上げたい。
養子縁組に残る差別
同性婚法が同性婚の当事者に認めた養子縁組は、結婚の相手方の実子を養子とする、いわゆる「連れ子養子」だけであり(同性婚法20条)、養子縁組に関するほかの民法規定の準用を規定していない。その結果、以下のような問題が残された。
まず、両名が共同で他人の子を養子に迎えたり、一方の養子を他方が重ねて養子にすることができない。従って、養子がいる者が同性パートナーと結婚しても、養子は片親のままでいることを余儀なくされる。すでに結婚した同性カップルが他人の子と縁組するには、まず離婚してからでなければ、一方だけで縁組を申請することはできない。配偶者のある者は配偶者と共同で縁組することとされているからである(民法1074条、夫婦共同縁組の原則)。これらの点は法改正によらなければ、解決できない差別的扱いである。
人工生殖法の適用
同性婚法には同性カップルに人工生殖法が適用になるかどうかについて明文規定がなく、衛生福利部(厚生労働省に相当)が今後、検討するとされる。解釈により少なくとも女性カップルには適用が可能とも思われるが、主管庁は法律が「夫妻」との文言を使っていることから、慎重な態度を崩さず、法改正を待つ必要があると解している。従って、同性カップルが台湾国内で人工生殖技術を使うことはできないのが現状である。もっとも、男性カップルを含めて外国での人工生殖による子作りを事実として禁止することはできない。法が婚姻を認めた以上は人工生殖による親子関係に関する法規律も不可欠なのであるが、現状では法の空白が続いている。
姻戚関係の適用
同性婚法は民法の姻族などに関する規定の準用の有無について規定していない。そのため同性の配偶者の場合、他方の血族との間に姻族関係が生じないことになる。この点について法務部はとくに対応していないことから、法律施行後、社会に混乱が発生している。たとえば、同性配偶者の父母が亡くなった場合、果たして職場で喪服休暇を取れるのかどうかがはっきりしない。職場の休暇に関する規則では、文言上、「配偶者の父母」と規定しており、「姻族」とは書かれていないことが多い。
同性配偶者の血族との間に姻族関係を生じさせないとすると、以下のような問題が発生する。①利害関係回避義務に関する規定では、「N親等以内の姻族」と規定されることが多いが、これに同性配偶者の血族を含めてよいかどうかが問題となる。たとえば、公職人員利益衝突回避法3条2号では「二親等以内の親族」を関係者と定めているが、同性配偶者の血族がこれに含まれるかどうかが問題となりうる。
②異性婚なら姻族にも一定の範囲で告訴権、証言拒否権など、親族としての権利が付与されることがあるが、同性婚の場合、親族関係にはないとすれば、これらの権利についてどう扱うべきかが問題となる。たとえば、犯罪被害者の告訴権を規定する刑事訴訟法232条では、2項で被害者死亡の場合にその二親等以内の姻族にも代理告訴権を認めている。これが果たして同性配偶者にも適用されるのかどうかが問題となりうる。
これらは立法による手当が必要な問題であろう。
信教の自由規定と差別の許容問題
同性婚法26条では、「いかなる者又は団体も法にもとづいて信教の自由及びその他の自由権を有し、本法の施行により影響を受けない」と規定した。信教の自由やその他の自由権は憲法13条、12条に規定されており、敢えて本法が規定する意味は本来なかったのであるが、同性婚法の制定にはキリスト教の信者を中心に反対論が強かったことに配慮して規定されたものである。しかし、本条を根拠に信教の自由を盾にとって、同性婚をした当事者を差別的に扱うことを正当化することが心配されている。たとえば、宗教団体が設立した学校や病院などが、同性と結婚した者について雇用を拒否したり、解雇したりといったことが起きはしないかである。果たして本条が将来こうしたことが問題になった裁判で、いかなる役割を果たすかは予想しがたい。